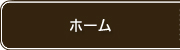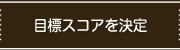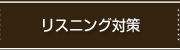もくじ
藻場再生の費用は誰が?
藻場造成の経済的効果は非常に高い反面、造成方法が適切でない場合は十分な効果が期待できません。お金は地方自治体や漁協が捻出しております。福岡県宗像市ではクラウドファンディングで資金を確保するような取り組みも行っています。
ただ、なかなか資金が集まらないというのが現状です。藻場再生というのはそんなに簡単にはいかないのです。藻場再生の技術的な問題だけでなく、資金の問題は非常に大きくなっています。
藻場再生を通して、地域の漁業を維持し、伝統的な海女の事業を維持することにも貢献しているのです。
藻場再生では何をしている?
藻場再生の方法はその状況によって異なることがあります。福岡県宗像市では鐘崎磯根においては藻を食べるウニ(ガンガゼ)を駆除したり、稚貝を放流したりしています。
このことで、藻場を回復させ、水産資源を守る取り組みを続けていますが、昔のようにはアワビ等が昔のようにたくさん捕れなくなっているのが現状です。
この藻場再生の動きを続けていくことで、少しでも水産資源を守ることが漁業を守ることでもあるので続ける必要があるのです。
藻場再生の取り組みの成功事例
岡山県日生町の種まきによるアマモ場再生
岡山県備前市日生町では、アマモ場再生のための取り組みが長年にわたり進められています。アマモは「海のゆりかご」と呼ばれ、浅海域の生態系を支える重要な存在です。しかし、沿岸部の開発や環境の変化により減少が進んでいます。この地域では1979年からアマモの基礎研究が始まり、漁業者や地元住民と連携して種まきを実施する活動へと繋がりました。 特に、種子の発芽促進技術の確立や移植基盤の開発により、発芽率や定着率を大幅に向上させることが可能になりました。この技術革新によって、再生されたアマモ場はCO2吸収量の増加や漁場の改善をもたらし、環境保全と漁業振興の両立を実現しています。こうした藻場再生の実例は、ブルーカーボンの可能性を示す良いモデルとして注目されています。
漁業者と行政の連携によるホンダワラ移植事例
ホンダワラを活用した藻場再生の取り組みは、鹿児島県奄美大島の瀬戸内町で注目されています。この地域では、観光業支援の一環として海底清掃活動と組み合わせて藻場再生プロジェクトが進行中です。特に漁業者と行政が連携し、地域全体でホンダワラを移植する活動が行われています。 ホンダワラはその高い生態系保全効果で知られ、移植が成功すると多くの海洋生物が集まる藻場を形成します。プロジェクトは新型コロナウイルスの影響を機に始まり、経済活動と環境保全の両立を目指して展開されています。このような協働の取り組みは、持続的な藻場再生モデルの構築に向けた好例と言えるでしょう。
鉄鋼スラグ活用型藻場再生の技術と成果
鉄鋼スラグを利用した藻場再生も、成功事例として注目されています。この手法では、鉄鋼スラグを海底に沈めることで、海藻の成長に必要な鉄分やミネラルを供給し、磯焼けした海域において藻場の再生を促します。 具体的な成果として、北海道での取り組みでは、鉄鋼スラグ設置後から数年内にアラメやカジメなどの海藻群落が回復し、それに伴って藻場が持つブルーカーボンのCO2吸収能力が増加したことが確認されています。この技術は廃棄物の有効活用と環境再生を両立させるものであり、持続可能な未来に向けた有望な手法とされています。
藻場再生のクラウドファンディング
藻場再生を行うにも費用は掛かります。それも継続性も必要です。そんな中、福岡県宗像市では寄付を募っています。これはふるさと納税を利用したクラウドファンディングとなります。
藻場再生の費用を寄付して頂いた方には「タコの柔らか煮」であったり、「天然アナゴの刺身」であったり、「天然トラフグのてっさ」となっています。
それでもなかなかお金が集まりません。このふるさと納税の知名度の問題なのか?それとも藻場再生に対する認識が広まっていないということなのでしょうか?このような働きかけはうまくいくことは大切ですが、多くの方に認知してもらうという面でも十分価値があると考えられます。
磯焼け対策と藻場再生についての関連記事
磯焼け対策と藻場再生に関するその他の情報はこちら。